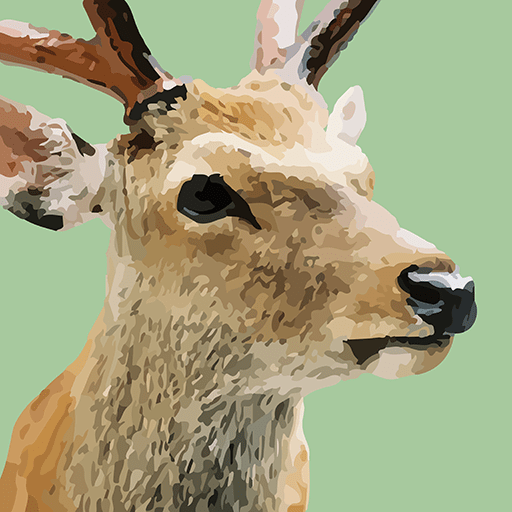どっかからきた僕たちが、ここからどっかへ行くだけの、つまんない場所だよ。絶え間なく水は流れている。ゆっくり昇る太陽の光がオレンジ色の雲の隙間から差し込んで、草も、花も、1本ずつ影を落とす。あらゆるものが立体的に立ち上がる。生きている気がしてしまう。そういう時間なんだ、午前4時って。悪い夢をみた。激しい動悸で目が覚めたが、夢だと気づいた瞬間には忘れてしまったので、「悪い夢をみた」ということしか覚えていない。そのことすら、やがて忘れてしまうだろう。ペットボトルの抹茶ラテが、絵筆を洗ったくらい濁っている。コンビニで、スポーツ新聞みたいに花束を売ってくれたらいいのに。
そういえば、元気かな?と思ってアカウントのページを覗くと半年ほどツイートがなかったが、「いいね」欄を見たら8月にいいねしてたから、なんだか安心してブラウザを閉じた。花瓶がないから、花を買えない。本棚の大きさは知識のキャパシティの可視化で、花瓶の大きさは心のキャパシティの可視化。他者を必要としているというより(都合のよい)他者を必要としているのであって、それを間違えると人間を頭の数で数えることになる。わかりあえないから他者なのに、わからない部分を無視してわかるところだけと付き合うのは、他者の身体を借りて自分の分身と話しているだけだ。
もしここが診察室で僕が医者なら、あなたは自身の不調を詳細に伝えようとするだろう。ここで大丈夫ではないと答えたところで、なにかしてくれると期待できない相手には、ほんとうのことを話す意味はない。だから、僕は大丈夫ですかと尋ねるのを合理的にやめて、あなたが大丈夫ではないと仮定して行動することにした。そもそも、僕たちは自身のことがよくわからない。嘘をつきたくてついているのではなく、正確にトラッキングできていないから、罪の意識なく平気で嘘をつける。あなたのことばを信用しない。でも、あなたのことは信じる。
ケチャップとマヨネーズを混ぜたオーロラソースのような色をしたオリジン弁当の椅子に座って、レシートに印刷された番号が呼ばれるのを待っている。1985番。西暦みたいだ。オリジン弁当の生姜焼きは生姜の香りがしなくて、かつて会社のオフィスの近くにあった中華料理屋の生姜焼きに似ていて、その中華料理屋は新型コロナウイルスが流行する前に閉店してしまった。閉店の理由はオリンピックによる開発で地価とテナントの家賃が上がったからだという噂だが、ほんとうかどうかはわからない。続けていても苦しかっただろうし、いつか閉じるならベストなタイミングだったのかもしれない。
発熱外来の場所を知らせる貼り紙に、花の挿絵をいれたほうがいいと思った人がいるんだよな、と思いながらテレビのニュースを眺めている。貼り紙の隅に挿絵をいれた人は、おそらく文字だけでは殺風景だと思ったのだろう。そして、いますぐに必要とされているこの場所にこそ、殺風景な紙を掲示するだけでは機能が足りないと思ったのだ。ラブホテルの外壁に埋め込まれたブラウン管のモニターに、無音のミュージックビデオが流れている。大丈夫。どっかからきた僕たちが、ここからどっかへ行くだけの、つまんない場所だよ。