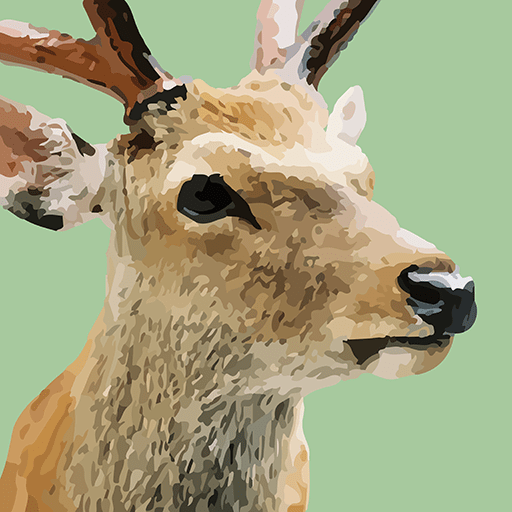恋だけでも甘いのに、大さじ一杯の愛を加える。沸騰した泡は積み重なって、鍋から吹きこぼれてガスコンロの火を消した。すこし開けた窓から差し込んだ低い光が、冬の冷たい部屋を照らす。物と物のあいだには、無数の光が満ちている。まぶしい。なるべく機嫌よくいたい。きれいな言葉を使いたい。ずっと過剰で、いつも足りない。いまの気持ちについて、このコンビニでいちばん近いものを買って帰るとするならば、ハーゲンダッツクリスピーサンド芳醇ティラミス。
愛はインタラクティブだから、愛した者だけが愛される。ずっと楽しみにしていたM-1グランプリも、なんだか笑えないような気がするんだ今年は。僕は、いつかの僕とはすっかり別人になっている。そして、それは僕が望んだことだ。連なったテールランプ、信号機、夜は赤い光に満ちていた。アスファルトに塗られた白線が消えかかっている。車や人の通りの多さが、横断歩道の劣化として記録されている。かすかな痕跡が集まって、世界の実感はつくられる。
浮かれているのかもしれないし、浮かれていたってかまわない。友達だとか恋人だとか、定義があいまいなラベルを維持するために、らしくないことをしてみたり、犠牲を払うなんて、関係性の奴隷だと思っていた。誰もいないエレベーターに乗り込めば、自然と鼻歌がでる。ということは、機嫌がいいのかもしれなかった。空が点滅している。雷鳴は聞こえない。それだけ遠くで雨が降っているのだ。電話をかけたまま眠りにつく、僕の耳の白いAirPods。
ぜんぜん別の場所にあるものが、重なって見える。いま起こっていることが、いつか体験したことのように感じられる。速すぎてよく見えないけど、出会った瞬間に別れている。それを繰り返している。からだの輪郭が高速に振動して、中と外が入れ替わっている。なんども死んでは、生まれ変わっている。それはそれとして、わたしたちはきょうも暮らしていかないとならないから、便宜上こんなことを恋愛と呼んでやりすごしているわけなのだが。
じゃあまたねバイバイ、と手を振りながら電車を降りて、それから帰り道をひとりで歩きながら、右手の感触を思い出していた。触れたいと思って、手を繋いでいい?と聞いたら、いいよと応えてくれたので、手を繋いだのだった。すこし強く握ると、握り返される力を感じた。手を伸ばせば触れられる距離に好きな人がいて、触れたいと思って、気持ちを受け入れてもらえたことが、うれしかった。その感触は、ふたりだけのものだった。